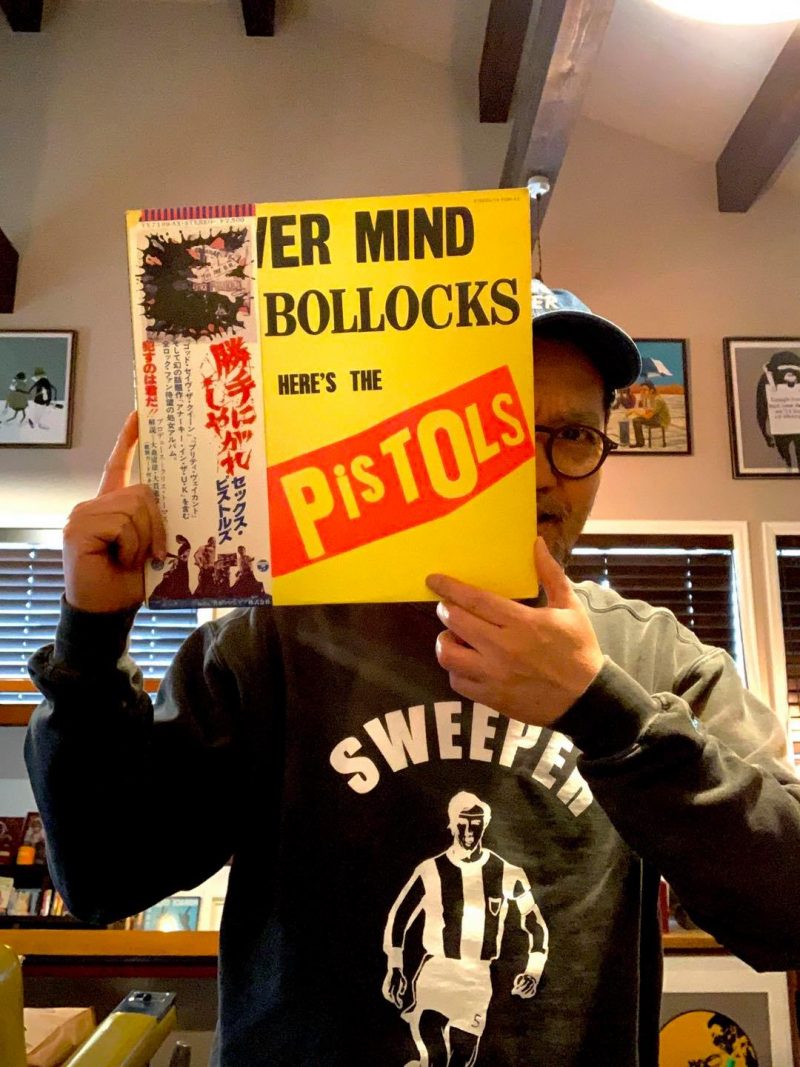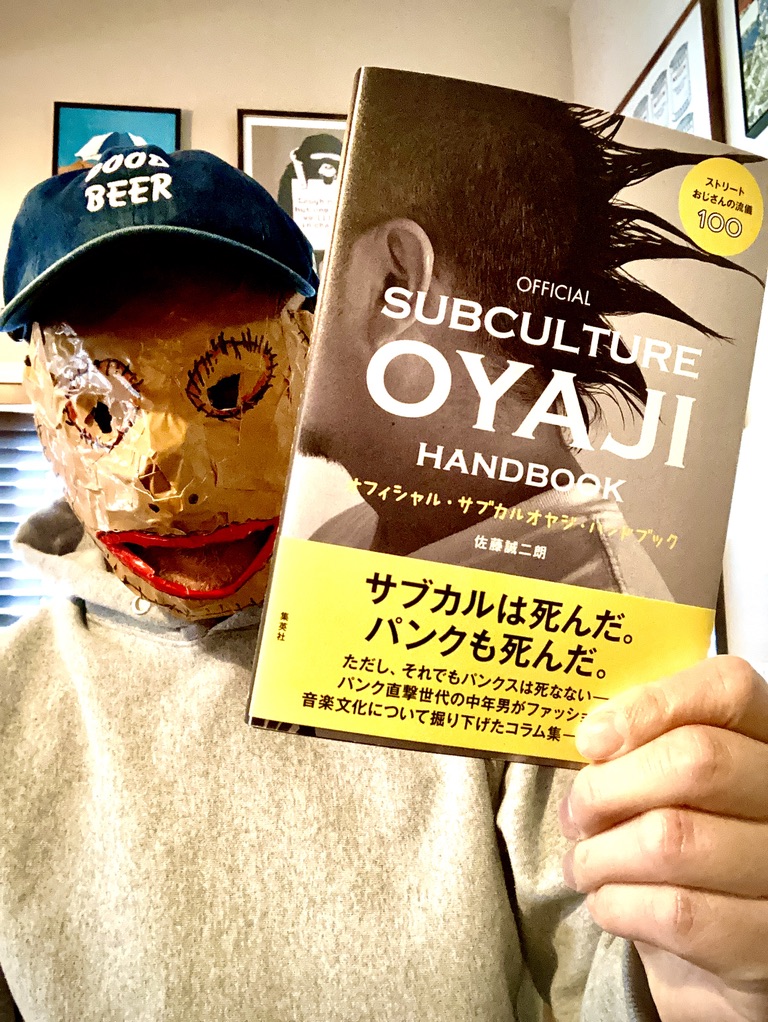息子の飼っていたヒガシニホントカゲの“イカボンド”が逝ってしまった。
ちょっと弱っているな〜と心配していた、シッポの短い“トガボンド”の方はいつの間にやら元気溌溂になり、元気だったはずの“イカボンド”が天に召される不思議。
これがあれか。
世の無常ってヤツか。
息子は「またトカゲ獲るぜよ!」と息巻いているが、息子よゴメン。
父さんは、なんだかやるせなくて気が乗らないぜ。
歳を重ねると、どうも手前勝手に眼前で起こる事象に意味を持たせたがるようになる。
とここまで書いてふと気付いた。
今自分がこうやって書き綴っていること、それはまさに吉田兼好先輩が言ってたアレなんじゃないかと。
先輩はこう言ったね。
“つれづれなるままに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ……”
現代語に変換すると
“することもなく手持ちぶさたなのにまかせて、一日中、硯に向かって、心の中に浮かんでは消えていくとりとめもないことを、あてもなく書きつけていると、(思わず熱中して)異常なほど、狂ったような気持ちになるものだ……”
って感じか。
そんなに手持ちぶさたでもないし、異常なほど狂ったような気持ちにはなってないけども、まさにこの感じじゃないかなと思った。
そうか。
オレは今、吉田兼好化が進んでいるんだな。
徒然し始めたってことなのか。
正直、書かなくてもイイ。
書かなきゃならないわけじゃない。
でも、書きたいのだ。
こうやって書き綴ることによって、なんか浄化されるっつーか、バランスが取れる感じがするのだ。
十一月に息子が植えたチューリップが咲いた。
いつの間にやら、外は春うららかだ。